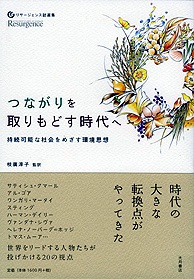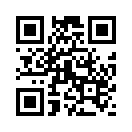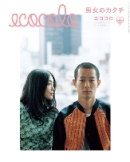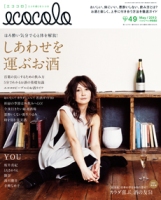2011年01月21日
2010年11月29日
旅行人 2011上期号
旅行人 2011上期号(No.163)です。
特集は「コーカサス」。旅ごころを誘う記事と写真が満載。
アルメニアの首都イェレヴァンからはアララト山が見えるようです。
他の記事も充実してます。
あと2号で終わりだなんで、ホント寂しいなぁ・・・

特集は「コーカサス」。旅ごころを誘う記事と写真が満載。
アルメニアの首都イェレヴァンからはアララト山が見えるようです。
他の記事も充実してます。
あと2号で終わりだなんで、ホント寂しいなぁ・・・

2010年11月21日
2010年10月30日
『減速して生きる ダウンシフターズ』
カフェの新しい本の紹介です。
『減速して生きる ダウンシフターズ』高坂 勝 著
ダウンシフターは著者の高坂さんの造語かと思って読み始めましたが、『浪費するアメリカ人』という本に登場していたそうです。
ダウンシフター=減速生活者
高坂さんさんは、ダウンシフトし、さらに、最近では米と大豆の自給も始められ、ますます理想的な生活をされているようです。
本の中にはいろんなエピソードが書かれているのですが、印象的だったのが、
伝統的発酵食品を食べ続けている親子が、他の人が全員発症したノロウィルスに発症しなかったお話。
体は食べたもので出来ている、を代表するような話だな、と思いました。
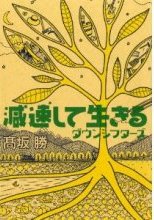
『減速して生きる ダウンシフターズ』高坂 勝 著
ダウンシフターは著者の高坂さんの造語かと思って読み始めましたが、『浪費するアメリカ人』という本に登場していたそうです。
ダウンシフター=減速生活者
高坂さんさんは、ダウンシフトし、さらに、最近では米と大豆の自給も始められ、ますます理想的な生活をされているようです。
本の中にはいろんなエピソードが書かれているのですが、印象的だったのが、
伝統的発酵食品を食べ続けている親子が、他の人が全員発症したノロウィルスに発症しなかったお話。
体は食べたもので出来ている、を代表するような話だな、と思いました。
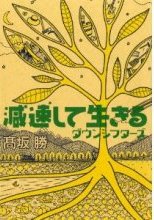
2010年09月20日
エココロ No.52
エココロ No.52。
特集は『夜のこと』
表紙は、映画『マザーウォータ』出演のもたいまさこさん、小林聡美さん、小泉今日子さん、市川実日子さん。
映画紹介の記事もあり、楽しい。10月30日から公開されるようなので、見に行きたいですね☆

特集は『夜のこと』
表紙は、映画『マザーウォータ』出演のもたいまさこさん、小林聡美さん、小泉今日子さん、市川実日子さん。
映画紹介の記事もあり、楽しい。10月30日から公開されるようなので、見に行きたいですね☆

2010年08月03日
ベルダvol.32 2010年秋号
ネパリ・バザーロさんから、フェアトレード・カタログ「ベルダ 2010年秋号」が届きました。
夏真っ盛りの暑い中ですが、秋のステキなフェアトレード・グッズを見るのも、いいものです。
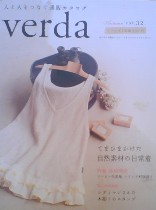
夏真っ盛りの暑い中ですが、秋のステキなフェアトレード・グッズを見るのも、いいものです。
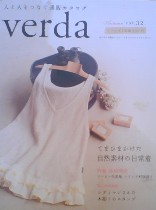
2010年07月20日
2010年06月16日
『しんしんと、ディープ・エコロジー』
ゆっくりノートブック第7段
SLOW & DEEP ECOLOGY
『しんしんと、ディープ・エコロジー』
~アンニャと森の物語~
今回はいつもの辻信一さんが、環境・平和運動家のアンニャ・ライトさんを迎えての対談形式です。
アンニャの生い立ちからこれまでの活動、ナマケモノや辻さんとの出会い・・・等々。
とてもステキな生き方をされている方
「Forest in Me」
「私の中の森を育てよう」という思いを込めて作られたというフレーズ。
心に響きます
『森の声キャンペーン』も展開されています。
アンニャにとっての「スロー」や「ディープ」であることは、「人間であるということを思い出すこと」。
それは例えば、自然豊かな場所で、ひとり自分と向き合う時間をつくることでもいい・・
辻さんも言っています、「human doing」になってしまった人間が、いかに「human being」に戻れるかと。
以前紹介した『スローライフのために「しないこと」』でも語られていた「すること」を、大切な「いること」の犠牲にしないために。
本の装丁も森をイメージできるデザインでとってもステキです

SLOW & DEEP ECOLOGY
『しんしんと、ディープ・エコロジー』
~アンニャと森の物語~
今回はいつもの辻信一さんが、環境・平和運動家のアンニャ・ライトさんを迎えての対談形式です。
アンニャの生い立ちからこれまでの活動、ナマケモノや辻さんとの出会い・・・等々。
とてもステキな生き方をされている方

「Forest in Me」
「私の中の森を育てよう」という思いを込めて作られたというフレーズ。
心に響きます

『森の声キャンペーン』も展開されています。
アンニャにとっての「スロー」や「ディープ」であることは、「人間であるということを思い出すこと」。
それは例えば、自然豊かな場所で、ひとり自分と向き合う時間をつくることでもいい・・
辻さんも言っています、「human doing」になってしまった人間が、いかに「human being」に戻れるかと。
以前紹介した『スローライフのために「しないこと」』でも語られていた「すること」を、大切な「いること」の犠牲にしないために。
本の装丁も森をイメージできるデザインでとってもステキです


2010年05月30日
旅行人 2010年下期号
旅行人 2010年下期号(162号)
いつも楽しみな『旅行人』。半年ぶりですね☆
今回の特集は「美しきベンガルの大地へ」
『ベンガル』=『バングラデシュ』+『インドの西ベンガル州』
編集長のレポートをはじめ、シャプラニールの職員の方のレポートや布や建物や陶器などいろんな角度から紹介されていて、読み応え満載です。
特集以外も興味深い内容がいっぱい


いつも楽しみな『旅行人』。半年ぶりですね☆
今回の特集は「美しきベンガルの大地へ」
『ベンガル』=『バングラデシュ』+『インドの西ベンガル州』
編集長のレポートをはじめ、シャプラニールの職員の方のレポートや布や建物や陶器などいろんな角度から紹介されていて、読み応え満載です。
特集以外も興味深い内容がいっぱい


2010年05月24日
かたりべからす
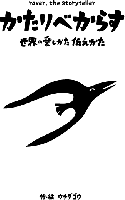
かたりべからす
~世界の愛しかた伝えかた~ 作・絵 ウチダコウ
--raven, the storyteller--
ウチダコウさんの絵と文章が語っています。
~~「お前の愛するものへ語りなさい。伝えなさい。」
Tell it to the one you love.Tell.
立ちつくしているだけじゃなく、伝えなくっちゃいけないんだなぁ・・・・とあらためて想います

2010年05月20日
エココロ No.50
エココロ No.50。
特集は「ベランダの森」。
いい感じのベランダやお庭が日常に溶け込んでる様子がいくつか紹介されています。
ベランダを充実させたくなりました
ちょっとさわってみよう・・・!

特集は「ベランダの森」。
いい感じのベランダやお庭が日常に溶け込んでる様子がいくつか紹介されています。
ベランダを充実させたくなりました

ちょっとさわってみよう・・・!

2010年04月15日
ベルダvol.31 2010年夏号
ネパリ・バザーロのフェアトレード・カタログ「ベルダ 2010年夏号」が届いています。
カフェでも使っているネパールのスパイスの特集もあります。
ネパールの有機農業の動きや、スパイスの流通、ネパリ・バザーロの取り組み等々興味深い内容です。
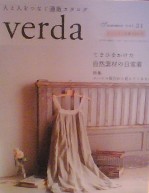
カフェでも使っているネパールのスパイスの特集もあります。
ネパールの有機農業の動きや、スパイスの流通、ネパリ・バザーロの取り組み等々興味深い内容です。
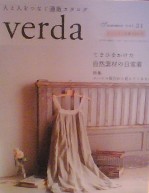
2010年03月20日
2010年02月21日
エココロ4月号(no.48)
エココロ4月号(no.48)。
特集:育てる、みんなのコドモゴコロ
“ホオポノポノ”を紹介しているページもありました。ハワイが生んだ奥深い知恵、“ホオポノポノ”。
少し前にホオポノポノについての本を読んだ私にとってはタイムリー感あり、です。

特集:育てる、みんなのコドモゴコロ
“ホオポノポノ”を紹介しているページもありました。ハワイが生んだ奥深い知恵、“ホオポノポノ”。
少し前にホオポノポノについての本を読んだ私にとってはタイムリー感あり、です。

2010年02月01日
『ベルダvol.30 2010年春号』
ネパリ・バザーロのフェアトレード・カタログ『ベルダ2010年春号』が届きました。
30号を迎えられたようです、おめでとうございます。
巻頭で、ネパリ・バザーロ代表の土屋さんが、ネパール東部のカンチャンジャンガ紅茶農園訪問予定時の、バンダ(ストライキ)により行けなかった模様などがリポートされていて興味深いです。
今号も友人が登場していてうれしい便り、でもあるのです

30号を迎えられたようです、おめでとうございます。
巻頭で、ネパリ・バザーロ代表の土屋さんが、ネパール東部のカンチャンジャンガ紅茶農園訪問予定時の、バンダ(ストライキ)により行けなかった模様などがリポートされていて興味深いです。
今号も友人が登場していてうれしい便り、でもあるのです


2010年01月23日
『スローライフのために「しないこと」』
月がきれいですね☆冬のいいところは、月がきれいに見えることかな。
今日は半月、なんかいつもよりちょっと小さいような・・・気のせい?ですよね(笑)
少し前にカフェの本棚に加わった『スローライフのために「しないこと」』(辻信一著)を紹介します。
「しないこと」からはじめよう、というメッセージが伝わってきます。
しないこと=しないでいること=「いること」
「すること」の反対は「いること」。
「いること」つまり、しないでいることが軽視されている現代に生きる我々に、「いること」の楽しさ、大事さをRemindしてくれています。
また、メッセージの中で、あらためて思ったのが「雑」の大事さ
雑談、雑事、雑用、雑学・・・
人生とは、そもそも雑用の集積のことではなかったのか・・と。
確かにそうだなぁ・・・と思います。
著者の辻さんが映画『かもめ食堂』の場面を引用しておられたことに、ちょっと親近感を覚えました。
私もいいな、と思っていた場面だったので。
ミドリ 「いいわね、やりたいことをやっていらして」
サチエ 「やりたくないことはやらないだけです」
先日、ご来店時にこの本を読まれていた方が、「いつも頭では思っているけど、こうして文字で読んだことで考えを整理できた・・」とおっしゃっていました

今日は半月、なんかいつもよりちょっと小さいような・・・気のせい?ですよね(笑)
少し前にカフェの本棚に加わった『スローライフのために「しないこと」』(辻信一著)を紹介します。
「しないこと」からはじめよう、というメッセージが伝わってきます。
しないこと=しないでいること=「いること」
「すること」の反対は「いること」。
「いること」つまり、しないでいることが軽視されている現代に生きる我々に、「いること」の楽しさ、大事さをRemindしてくれています。
また、メッセージの中で、あらためて思ったのが「雑」の大事さ

雑談、雑事、雑用、雑学・・・
人生とは、そもそも雑用の集積のことではなかったのか・・と。
確かにそうだなぁ・・・と思います。
著者の辻さんが映画『かもめ食堂』の場面を引用しておられたことに、ちょっと親近感を覚えました。
私もいいな、と思っていた場面だったので。
ミドリ 「いいわね、やりたいことをやっていらして」
サチエ 「やりたくないことはやらないだけです」
先日、ご来店時にこの本を読まれていた方が、「いつも頭では思っているけど、こうして文字で読んだことで考えを整理できた・・」とおっしゃっていました


2010年01月21日
2009年12月26日
『地球のレッスン』 北山耕平 著
最近発行された北山耕平さんの『地球のレッスン』。
今の生活をもうすこしましな方に変えたいひとの役に立つように作られたという、『自然のレッスン』の姉妹本とも言える本で、
「地球に生きる人間」に還るとあらためて心を決めたひとに贈る~ (帯より)、という素敵な1冊です。
『自然のレッスン』同様、時々手にとってみたいと思います。
1回読んだところでは、涸れ井戸に落ちたロバの話が心に残っています。
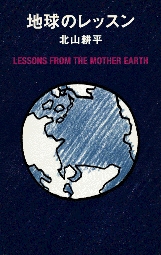
今の生活をもうすこしましな方に変えたいひとの役に立つように作られたという、『自然のレッスン』の姉妹本とも言える本で、
「地球に生きる人間」に還るとあらためて心を決めたひとに贈る~ (帯より)、という素敵な1冊です。
『自然のレッスン』同様、時々手にとってみたいと思います。
1回読んだところでは、涸れ井戸に落ちたロバの話が心に残っています。
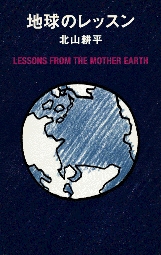
2009年12月20日
エココロ2月号(no.46)
エココロ2月号(no.46)。
特集は、真冬の読書。
室内で本を読む季節ですねぇ・・・気になっていた本を手に取ってみましょう
第2特集は、ナチュラルおそうじ手帖。お掃除の季節でもありますね・・やらなきゃ(笑)
表紙はUA。いいですねぇ。

特集は、真冬の読書。
室内で本を読む季節ですねぇ・・・気になっていた本を手に取ってみましょう

第2特集は、ナチュラルおそうじ手帖。お掃除の季節でもありますね・・やらなきゃ(笑)
表紙はUA。いいですねぇ。

2009年12月08日
『つながりを取りもどす時代へ』
今日は最近カフェの本棚に入った本を紹介します。
いろんな問題について知ったり、それについて自分に何ができるかを考えたり、持続可能な生活を目指すために多くの学びを与えてくれる本だと思います。
目次を見て、興味がわいた箇所を読んでみるだけでも、気づきを得られると思いますので、ひとやすみして手にとってみてくださいね☆
『つながりを取りもどす時代へ』~持続可能な社会をめざす環境思想~
40年以上の歴史を持つ環境をテーマとした英国の雑誌「リサージェンス」から厳選された記事の日本語版です。
この「リサージェンス」の編集長を長くつとめておられるのは、「Soil、Soul、Society(土、心、社会)」のサティシュ・クマールさん。精神性を取り戻すことの必要性を説いておられます。世界の60億人が西側諸国のような暮らしをしてエネルギーを使うと地球が5個必要になってしまう、こんな物質主義の社会はどう考えても持続可能ではないから。。
厳選された20の記事の執筆者は、持続可能な社会を考える中で目にすることが多い様々な分野で活躍する方々。
米国の農業の補助金による被害についての記事を書いているのはクレーグ・サムズさん。米国でトウモロコシと大豆の補助金が撤廃されただけでも1ドルのハンバーガーの値段は3ドルになり、ファストフードの食べ方も変わるだろうと。
種子の偉大さについて述べているのはヴァンダナ・シヴァさん。生物多様性の保全と、農民による種子の保護と分かち合いを促進する運動「ナブタニャ」を進めています。
ラダックから学び 『ラダック 懐かしい未来』や『いよいよローカルの時代』でおなじみの、グローバル化からローカル化への転換を進めるヘレナ・ノーバーグ=ホッジさん。経済のローカル化は、人々に幸福感をもたらします。
流行がもたらす犠牲についての記事は、チャーティー・デュラントさん。ファストファッションが環境と社会に多大な影響を及ぼしていると。衣類の布地の染料や漂白剤から有害な化学物質が土壌に流れ込むなどして起こる環境汚染、安い労働力を求めるためにもたらされている労働災害。
私が初めて耳にした言葉は「バイオミミクリ」。
ジャニン・ベニスさんが書かれています。バイオミミクリとは、自然について学ぶのではなく、自然から学ぶこと。周囲にある自然という天才と別々に存在しているのではなくてその一部である機会も与えてくれる。自然から学ぶ中で、普段は交流のない分野の専門家がお互いからも学ぶことで、極端でなく自然にもやさしいアプローチができるということ。排水浄化処理会社の研究者をガラパゴス諸島に連れて行き、彼らが自然から学んだ様子がおもしろいです。
先住民族の尊厳の宣言については、ジェリー・マンダーさん。
2007年9月13日に国連で、尊厳の宣言・「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたそうです。
交渉が始まって25年。賛成144、反対4、棄権11、反対は米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド。先住民族の領土の鉱山などの開発権を持たせないための反対。
先住民族が置かれた状況は地球の生態系の危機を分けて考えることができない。資源が搾取されたのは大部分が先住民族の地で起きており、資源が枯渇してきている事実。先住民族宣言には強制力がありませんが、今後各国がこの宣言を正式に受け入れて成文化することが次のステップです。
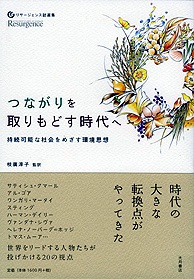
いろんな問題について知ったり、それについて自分に何ができるかを考えたり、持続可能な生活を目指すために多くの学びを与えてくれる本だと思います。
目次を見て、興味がわいた箇所を読んでみるだけでも、気づきを得られると思いますので、ひとやすみして手にとってみてくださいね☆
『つながりを取りもどす時代へ』~持続可能な社会をめざす環境思想~
40年以上の歴史を持つ環境をテーマとした英国の雑誌「リサージェンス」から厳選された記事の日本語版です。
この「リサージェンス」の編集長を長くつとめておられるのは、「Soil、Soul、Society(土、心、社会)」のサティシュ・クマールさん。精神性を取り戻すことの必要性を説いておられます。世界の60億人が西側諸国のような暮らしをしてエネルギーを使うと地球が5個必要になってしまう、こんな物質主義の社会はどう考えても持続可能ではないから。。
厳選された20の記事の執筆者は、持続可能な社会を考える中で目にすることが多い様々な分野で活躍する方々。
米国の農業の補助金による被害についての記事を書いているのはクレーグ・サムズさん。米国でトウモロコシと大豆の補助金が撤廃されただけでも1ドルのハンバーガーの値段は3ドルになり、ファストフードの食べ方も変わるだろうと。
種子の偉大さについて述べているのはヴァンダナ・シヴァさん。生物多様性の保全と、農民による種子の保護と分かち合いを促進する運動「ナブタニャ」を進めています。
ラダックから学び 『ラダック 懐かしい未来』や『いよいよローカルの時代』でおなじみの、グローバル化からローカル化への転換を進めるヘレナ・ノーバーグ=ホッジさん。経済のローカル化は、人々に幸福感をもたらします。
流行がもたらす犠牲についての記事は、チャーティー・デュラントさん。ファストファッションが環境と社会に多大な影響を及ぼしていると。衣類の布地の染料や漂白剤から有害な化学物質が土壌に流れ込むなどして起こる環境汚染、安い労働力を求めるためにもたらされている労働災害。
私が初めて耳にした言葉は「バイオミミクリ」。
ジャニン・ベニスさんが書かれています。バイオミミクリとは、自然について学ぶのではなく、自然から学ぶこと。周囲にある自然という天才と別々に存在しているのではなくてその一部である機会も与えてくれる。自然から学ぶ中で、普段は交流のない分野の専門家がお互いからも学ぶことで、極端でなく自然にもやさしいアプローチができるということ。排水浄化処理会社の研究者をガラパゴス諸島に連れて行き、彼らが自然から学んだ様子がおもしろいです。
先住民族の尊厳の宣言については、ジェリー・マンダーさん。
2007年9月13日に国連で、尊厳の宣言・「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたそうです。
交渉が始まって25年。賛成144、反対4、棄権11、反対は米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド。先住民族の領土の鉱山などの開発権を持たせないための反対。
先住民族が置かれた状況は地球の生態系の危機を分けて考えることができない。資源が搾取されたのは大部分が先住民族の地で起きており、資源が枯渇してきている事実。先住民族宣言には強制力がありませんが、今後各国がこの宣言を正式に受け入れて成文化することが次のステップです。